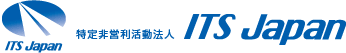第6回ITS地域交流会 in 富山2014(2014年8月19日)
【第6回 ITS地域交流会 in 富山2014 開催報告】
~地域が目指すまちづくりに、進化するITSやクルマの活用を考える~
2014年8月19日、富山市において“ITS地域交流会 in 富山”を開催した。
1.実施概要
日本の地方都市では移動や交通等の生活課題を解決しつつ、産業力を高めて活力のある持続可能なまちづくりが求められている。一方、近年Openプラットフォームを活用した交通情報システムや、高度な運転支援技術を搭載したクルマの進化が加速している。地域が目指す街の姿と、それに対してどのようなシステムやクルマが求められていて、地域ではそれをどう活用し、また作ればいいのであろうか。
6回目となる今回は、「地域が目指すまちづくりに、進化するITSやクルマの活用を考える」をテーマに、富山県および県内自治体の交通政策、道路管理、情報政策、工業振興等の担当者と、ITSに関心がある事業者、大学生、市民の立場で高校生も参加対象者として、有識者による講演と地域で取組まれている具体的な施策の事例紹介をしたいただき、それをきっかけにして参加者全員で「暮らしやすく移動しやすい魅力あるまちづくり」をテーマにグループディスカッションを行った。
1) 日 時:2014年8月19日【火】13:00 ~ 17:30
2) 会 場:パレブラン高志会館(富山市内)嘉月の間
3) 参加者:富山県および県内自治体の交通政策、道路管理、情報政策、工業振興等の担当者と
ITSに関心がある事業者、大学生、市民の立場で高校生
4) 参加人数 : 国土交通省(5名)、経済産業省(1名)、富山県(4名)、富山県内の
市町村(5名)、大学の教員と学生(10名)、高校生(11名)、
登壇者(6名)、地元企業(18名)
5) プログラム:配布プログラム
第Ⅰ部 講演
第Ⅱ部 事例紹介
第Ⅲ部 ディスカッション ~暮らしやすく移動しやすい魅力あるまちづくり~
・グループディスカッション(グループに分かれて、参加者同士で議論)
・登壇者への質疑、パネルディスカッション、全体ディスカッション
(登壇者や他の参加者との討議、質疑応答)

2.講演内容
2-1)講演
1) 公共交通とまちづくり
(富山大学 芸術文化学部長 教授 武山 良三 氏 )
2) 自動運転車の開発現状と地方のくらしへの貢献
(一般財団法人日本自動車研究所 ITS研究部 主席研究員 青木 啓二 氏)
2-2)事例紹介
1) 塩尻市が考える情報収集・配信のデザイン~情報の収集の重要性と可能性~
(塩尻市 協働企画部 情報推進課 専門幹 金子 春雄 氏)
2) 交通インフラ設計のためのマルチエージェントモデルと全体最適化
~富山のひと一人一人の交通行動をまるごとシミュレーション~
(富山県立大学 工学部 情報システム工学科 准教授 榊原 一紀氏)
(神戸大学 工学部 研究員 松本 卓也氏)
3) 自然エネルギーの地産地消による地域の活性化を目指して
(社団法人でんき宇奈月プロジェクト 代表理事 大橋 聡司氏)
3.ディスカッション
3-1) グループディスカッション
参加者と登壇者が8つのグループに分かれて、講演内容や事例紹介、地域の交通課題に
ついてグループ毎に討議・意見交換を行い、結果を発表した。
3-2) パネルディスカッション、全体ディスカッション
登壇者全員がパネラーとなり、富山大学工学部長の堀田教授をモデレータとして
パネルディスカッションを行った。
また講演や事例紹介内容への質疑応答、補足説明等も行った。
主な議論
◎公共交通の課題やあるべき姿、捉え方についてのグループディスカッションでの意見
- 街に魅力が無いとどんなに交通を整備しても人が集まらない。
- バス利用者の高校生から「バスが朝混んでいて乗れない」と聞き、普段自動車しか使っていない大人には驚きと気付きがあった。
- 混み合う時間帯のバスの最適配車にITS活用が必要。
- 複数の交通機関の乗継ぎが良くない事がある。乗継を考慮した交通シミュレーションをやってもらって最適ダイヤができるといい。
- バス停も電停も、誰が見ても一目でバス停だ、電停だとわかるような色形デザインに整備できたらいいと思う。
- 富山地方鉄道線のLRT化について議論したが、料金や運行本数などニーズを明確にして、住民もどうやったら路線が維持できるか税金だけに頼らない体制作りが必要。
- 「公共交通はコミュニケーション空間である」という武山先生の話に合点した。
- 富山市の場合、郊外から郊外へ移動する時に市の中心部を経由するしかないのは不便。
◎自動運転ができた時に富山はどう変わるか、についてのグループディスカッションでの意見
- 自動運転車は高齢者の免許返上後をサポートする乗り物になるだろう。
- 水平エスカレータという考え方で狭いエリアの人や物の移動運搬の手段に成り得る。
- 今のクルマにはまだまだ足りない機能がある。例えば走行中に前の車が止ろうとしている時、左折したいのか右折したいのか、方向転換したいのか、が分らない。周囲にそれを伝える新しいサインがあっても良いのではないか。
- 駐車場の中で所定の場所に自動で停めてくれる機能があれば利用されるのではないか。
- 高齢化が進むので自動運転カーへの期待は大きいが機械任せに心配がある。飛行機でも人が管制をしている。住民が納得できる政策にする必要があり、コミュニケーションの場が大事。
- 完全自動化したら子供が勝手に遠出してしまう危険がある。
- 完全自動化した時に起きた事故の責任はだれが負うのかについては、年間の交通事故死者数が自動運転によって減ったならば(国家目標を達成しているので)責任は自動運転システムを推進した国が負えばいいのではないか。
- 自動運転の時代には自動運転車両用の専用道路はLRT起動を転用して作ってはどうか。
- 白線検出で自動走行するのは雪が降る冬や、除雪で白線が剥がれる春先は大丈夫か?
- 自動運転を高齢者が使うと頭を使わなくなってバカになりはしないか心配あり。
- 郊外の自治体では自動運転で移動の人件費が抑えられるのでメリットがあるが富山市のようにコンパクトシティを目指す場合には郊外にも移動しやすくなるので政策と相反するという難しさがある。
◎講演と事例紹介の内容への質疑応答
Q:自動運転技術の方式は統一されたり、技術や特許が公開される可能性はあるか?
A:普通は出来上がった技術を後で標準化するものだが、自動運転についてはアメリカ中心に
効率化のために標準化を先にやる動きはある。技術そのもの標準化ではなく自動運転の
カテゴリ毎の性能や機能の標準化になるのではないか。
Q:富山地方鉄道はLRTに変えた方が良いのか?
A:普通の鉄道に比べてLRTは踏切や駅舎がいらないというコストメリットがある。
公共交通は運行本数が鍵で、一時間に最低3本できれば4本走らせたい。そのためも
LRTにして本数を増やした方が利用者が増える。高岡市のLRTの実績からもそう言える。
◎モデレータの堀田先生による富山市内のLRTとバスのリアルタイム位置表示デモ
- 昨年度の産官学による成果。地方都市で路面電車のリアルタイムロケーション表示ができる事例はまだあまりない。富山地方鉄道の本線とも連携を取って富山県内全体の交通の運行状況を加味して待ち時間の無い経路ナビゲーションをするシステムが構築できる。富山市だけでなく高岡市や黒部市でも使えるようにしていきたい。
◎登壇者によるパネルディスカッション
※移動しやすく暮らしやすい魅力ある富山のまちづくりについて各氏にコメントをいただいた
(コメント1)
- 現代は満ち足りている状態。技術というものは楽しいのでつい忘れがちになるが、人々が何を求めているか、何が必要なのか、心躍らせるものは何なのか?を問うべき。答えは「人々の繋がり、交流の中から生まれてくる価値」だと思う。
- マイカーで移動する人はおしゃれをしなくなる。すると街から華やいだ雰囲気が消える。公共交通でおしゃれな人と出会うのは楽しいもの。
- 不特定多数の色々な人が色々な形で出会うのが街の楽しさ。富山の人が多様性を楽しみつつそこから新しい物を創って行くような街づくり、そこから逆算して都市は、ITSはどうあるべきかを考えることが大事。
(コメント2)
- 富山市のような都市部では自動運転はいらないと思う。
路面電車と自動車の共生をどう進めるかが重要。
互いが通信して、路面電車が近づいたらクルマが自動で減速する等の機能が考えられる。 - 富山市以外、全国の過疎地域では、高齢化が進み交通弱者問題が出てくるので自動化の活用の場があると考える。具体的にどう走らせるかは難しいが地域で検討してもらいたい。
(コメント3)
- 高校生のバスの話でも、満員で乗れないバスとガラガラのバスがある。
交通のデータを取って色分けして見てみて路線をどうするかを決めれば首長の勝手な意見だとは言われない。 - 高齢化対策を含めた街づくりは今後高齢化してくる世界の国に対して売れる。
- 新幹線開業で人の流れが変る。これを機に交通のデータ化をして、高速大量輸送と少量輸送について数学の知識を使えば2020年の五輪で地方にも来る世界の観光客対応にも役立つと思う。
(コメント4)
- まちづくりの手伝いできるツールを作りました。
- 高校生以下の生徒は自転車や徒歩での通学が多いが冬や雨の日はバスと市電を乗り継いで通学している。地域がクルマ社会になると高校生は大変だと思った。
- 交通間の連携が重要という話があったが、現在のシミュレーションモデルには交通手段間の連携が入っていない。今後は入れた方がいいとヒントをもらった。本当に利便性の高い交通のあり方をシミュレータを使って考えて行きたい。
- 富山だと夏と冬では交通の様子ががらっと変ると思う。そういう地域毎の実際の人の動きの事情が必要なので地元の方々に協力していただきたい。
(コメント5)
- 移動しやすさについては、東京から宇奈月にくるときの乗継がとても悪い。これを少し変えるだけで大分よくなる。交通事業者の部分最適でなく全体最適で考えると変ってくる。
- くらしやすさについては、中山間地は高齢化が進み、自分で運転できない人が病院や公共施設にいく方策としてコミュニティバスをやっているが、今後はオンデマンドバスにして運行効率を上げる必要がある。運行コストは人件費と燃料費なので小水力発力や再生可能エネルギーを使い、自動運転で人件費を抑えていくことになればいい。
山の荒廃を防ぐために中山間地にも一定数の居住人口は必要である。 - 魅力あるまちづくりについては、現在各旅館や事業者がやっている駅までの送迎をEVバス(水平エスカレータ)を巡回させてまかなおうとしている。時速19kmで巡るので事故が置きにくく安全面でも寄与する。
◎会場からパネラーへの質問
Q:電車に乗れたり物も買えたりするカードは富山にはできないのか?(高校生より質問)
A:限られた人だけでなくそこに居る人全部(まちや、大学や職場等)で公共交通を
支えるとうまくいく。
シアトルのワシントン大学のUパスは街中のバス乗り放題でも安い。
学生が街中で飲んだりするので街の利益にもなる。
公共交通は交通だけでなく地域全体の産業の中で考えていく必要がある。(武山氏)
◎モデレータの堀田教授のコメント
- 国土強靭化政策が打ち出されているが、富山は災害が少ないので都会をバックアップできる機能を持っている。大きな災害に対して富山は行政も産業もやれることが沢山ある。
- 今回のITS交流会は富山の交通だけでなく色々な事例を紹介し、産官学が意見を交わす場となった良い機会だった。
- 今回は私の発案で利用者目線で高校生にも参加してもらったが色々な世代の人と話ができて良かったと思う。彼らもよく頑張ってくれた。これからの進路において良い経験になると信じている。
4.最後に
ITS地域交流会ではこれまで行政の担当者と講師とが一緒になってテーマに関するグループ討議を行う形を取ってきた。近年は地元の民間企業や交通事業者にも参加いただいてディスカッションをすることもあったが、今回は市民の目線、公共交通利用者の目線での意見を求めて、初めて大学生、高校生にも参加していただいた。
普段接点が少ない異業種の企業同士、産官学民の異なる立場同士、さらには高校生を含む幅広い世代の参加者、が一堂に会して同じテーブルを囲んでのディスカッションでは、予想を超えた熱心な意見が交わされ、富山の交通まちづくりとITSの利用シーンについて、さらに自動運転のクルマが走る将来の地方のまちの姿について立場と世代を超えて考える場となった。
本交流会での議論や、本交流会で生まれた産官学民の新しい人の繋がりが、今後の地域モビリティやまちづくりへのITS/ICT技術の活用、地域特性に合った政策の立案や実施等、参加者各位の業務に役立てば幸いである。
《 参考資料紹介 》
・ITS地域交流会とは?(ITS Japanの地域ITS活動)
・ITS Japanについて